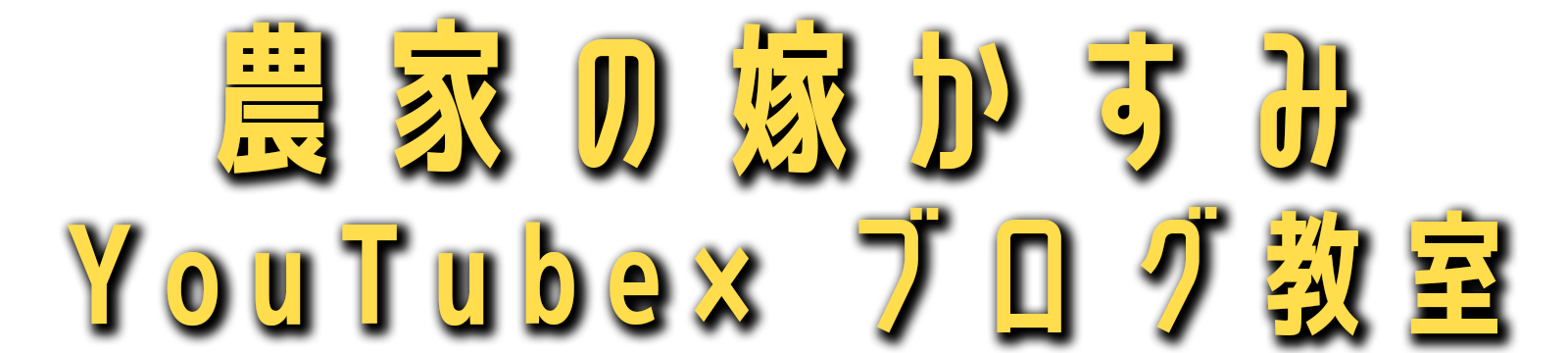- YouTubeで伸びる人と伸びない人の違いを知りたい
- 伸びる人になるためにやるべきことは?
- YouTubeの伸ばし方を知りたい
近年の副業ブームの中でYouTubeに注目が集まっていますが、本業・副業に関わらず、YouTubeに取り組み始めてしばらく経つと伸びる人と伸びない人とで明確な差が生まれてきます。
稼ぐことができると言われるYouTubeですが、適切なやり方を知らなければ伸ばすことはできません。
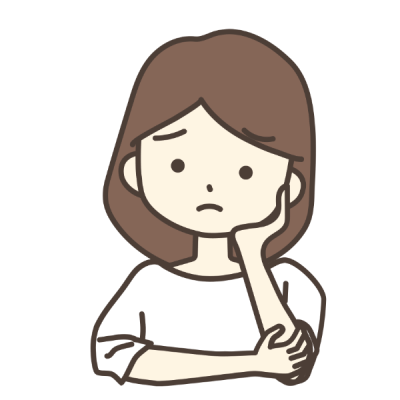
YouTubeを始めたものの思うように伸びず…
同時期に始めて伸びている人もいるようなので違いについて知りたいです。
この記事では、YouTubeで伸びる人と伸びない人の違いとは何かを徹底的に解説。
伸びる・伸びないを分ける大きな差や伸びない人が伸びる人になるためにやるべきことも紹介しています。YouTubeを今よりもっと伸ばしていきたい方、必見の内容です。
それではさっそく見ていきましょう。


ノースキルの主婦でも顔出し、声出し、名前出しなしで月100万円を安定的に稼ぐことのできるロードマップを配布中。解説動画と74ページの電子書籍で主婦の副業をサポートします‼︎
\ 今だけ期間限定配布中 /
YouTubeで伸びる人と伸びない人の3つの違い(技術面)
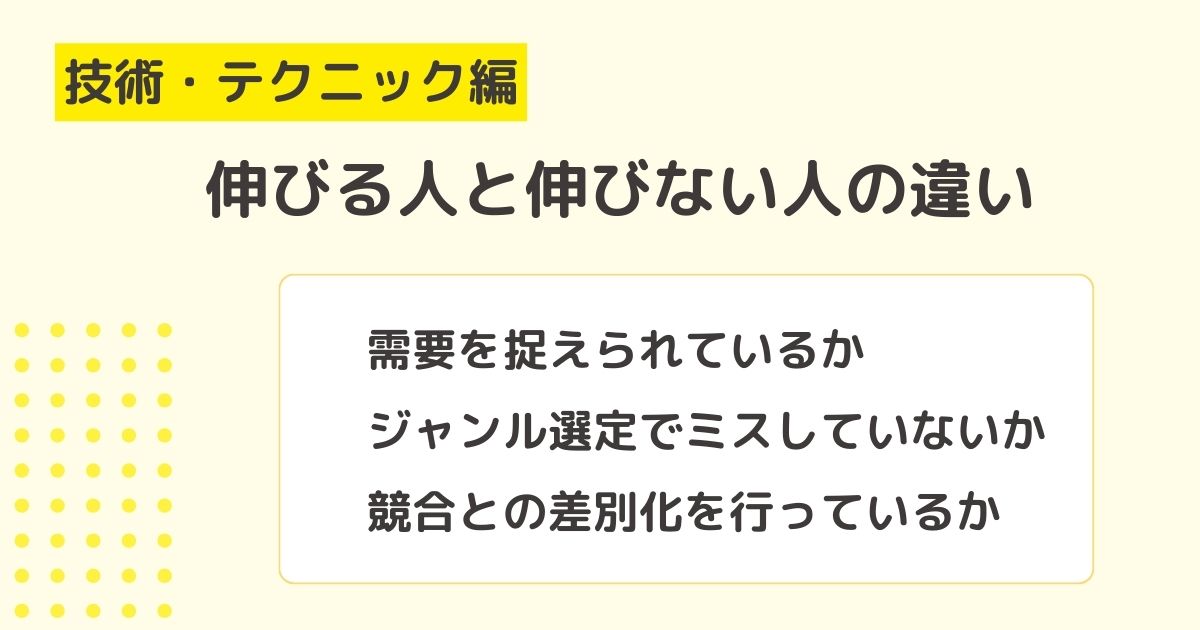
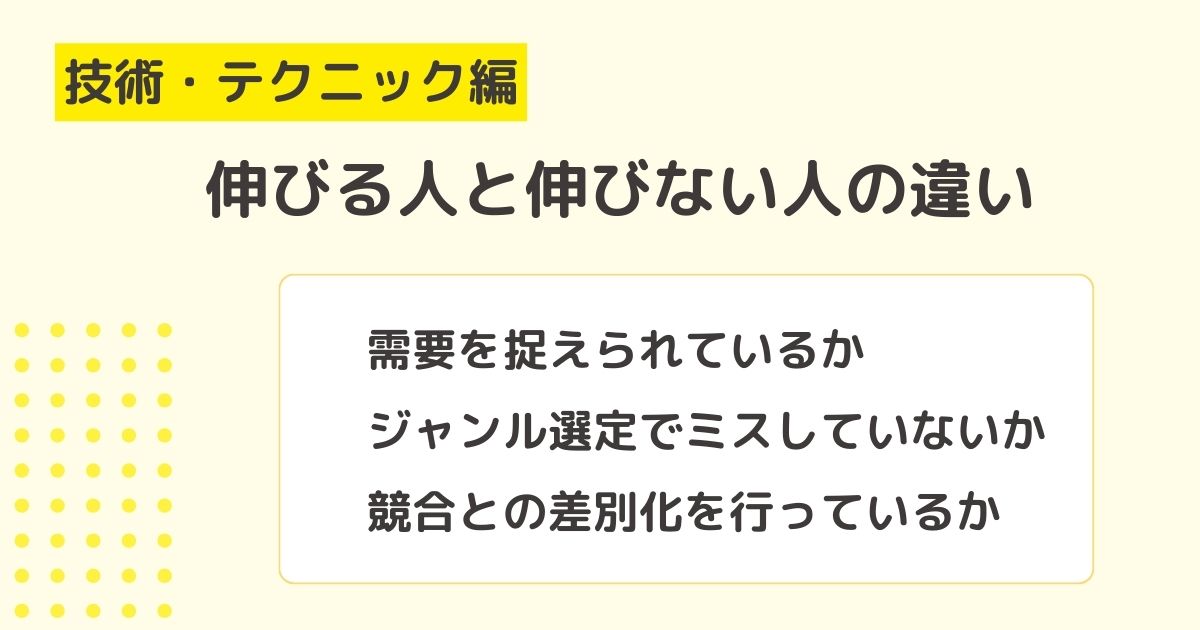
YouTubeで成功する人と伸び悩む人の間には、明確な違いがあります。
単なる運や才能だけでなく、戦略的なアプローチと継続的な努力が成功への鍵となるでしょう。
- 需要を捉えられているかどうか
- ジャンル選定でミスしていないか
- 競合との差別化を適切に行えているか
ここでは、まず上記の技術的な問題に焦点を当てて、伸びる人と伸びない人の具体的な違いを比較しながら詳しく見ていきます。
需要を捉えられているかどうか
YouTubeで伸びる人の最大の特徴は、視聴者が求めている「需要」を的確に捉えていることです。
YouTubeで稼ぎたいのであれば、収益につながるかを意識して視聴者のニーズと向き合わなければいけません。
多くの伸びない人は、何となく自分が作りたいものを優先してしまう傾向にあります。



成功するためには、「自分が作りたいコンテンツ」と「視聴者が求めているコンテンツ」のバランスを取ることが重要です!
完全に需要だけを追求すると個性が失われるかもしれませんが、完全に自己満足だけを追求すると視聴者を獲得できません。
需要のリサーチをしていなかったり、ニッチすぎるテーマを選択したりすると、伸ばす難易度は格段に上がります。
自分の強みを活かしながらも、大前提として視聴者の需要を満たすコンテンツを提供しましょう。



単に自分が面白いからという理由だけでコンテンツを作成しないように気をつけた方が良いのですね。
ジャンル選定でミスしていないか
需要と同じように、選ぶジャンルによってYouTubeで伸びるかどうかの差が出てきます。
YouTubeでジャンルを選ぶ際には次のような点に注意が必要です。
- 自分の専門性や情熱とのマッチング
- 需要と競合のバランス
- 成長性のあるジャンル
- 収益化しやすいジャンル
自分が詳しい分野や情熱を持っている分野を選べば、質の高いコンテンツを継続的に作成できます。
さらに、市場のトレンドもYouTube運用に大きな影響を与えるポイントのため、一時的なブームで終わるのではなく、長期的な視点を持ちましょう。
例えば、おすすめのジャンルとして紹介されることが多い下記のジャンルですが、トレンドや状況に応じて注意が必要です。
| ジャンル | 注意点 |
|---|---|
| スピリチュアル | スピ系は稼げると紹介されているが、その分競合も多い。訴求やユーザーの理解が必要。 |
| 焚き火 | Xなどで非属人の動画としておすすめされることがあるが、今からでは旬をすぎているため遅い。 |
| 都市伝説 | 内容が事実と異なるとみなされると収益化が剥奪ことがあるので、YouTubeポリシーの変更の影響を受けやすい。 |
| AI系 | 需要は高くトレンドだが、競合も多い。 特にツールやテクノロジーの発展が早いため、すぐに情報が古くなる。 |
| 有名人の切り抜き動画 | 切り抜き動画自体の収益化が許可されていないため、長く安定的に稼ぐ上で不利。 「◯◯さんの切り抜きが良い」と情報が出回るが、競合もすぐに現れて飽和する。 |
自分との相性に加えて環境要因も踏まえてジャンル選びを進められると運用で大きなアドバンテージを得ることができます。
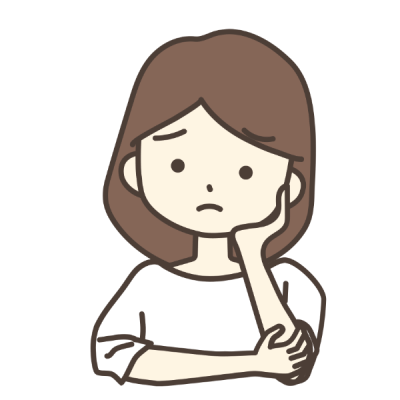
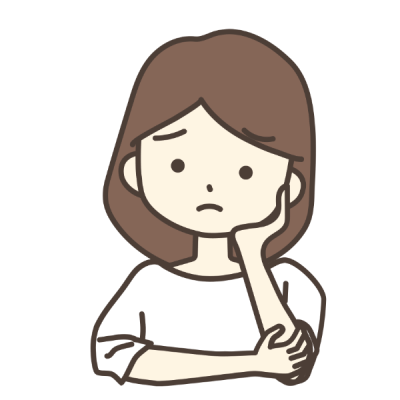
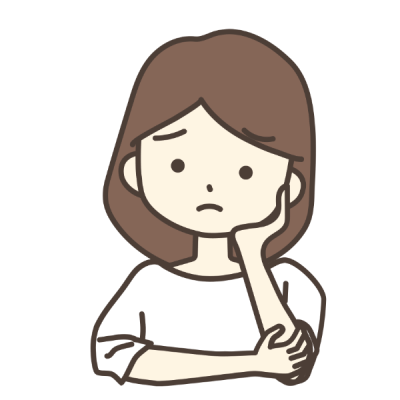
具体的におすすめのジャンルはありますか?



おすすめはズバリ「朗読系ジャンル」です!
朗読系YouTubeは、人気小説や名作・絵本・動画などを朗読して配信するもので、収益化において次のようなメリットのあるジャンルです。
- 高齢層を中心とした視聴者で広告単価が高い
- 動画再生時間が長くなりやすい
- 制作コストを抑えられる
収益化条件を達成しやすく、YouTubeで大きく稼ぎたいという人に向いています。
また、外注化を進めることができるため、時間のない社会人や主婦の方でも挫折せずに続けやすいでしょう。



公式LINEではノースキルから朗読系YouTubeで稼ぐノウハウを特別に発信しているので、ぜひご覧ください。
>>朗読系YouTubeのノウハウを見る
競合との差別化を適切に行えているか
YouTube運用において一つの課題となる「差別化」を伸びる人は効果的に行っています。
他の動画のパクリばかりをしていると、コピーコンテンツとみなされ収益化の審査に落ちてしまう場合も。
また、視聴者にとってもマンネリ化した動画はつまらなく感じるため、動画やチャンネルが伸び悩む原因になりえます。
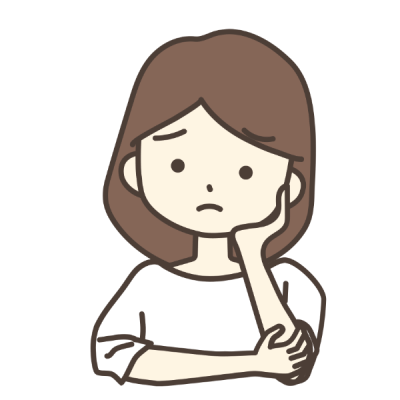
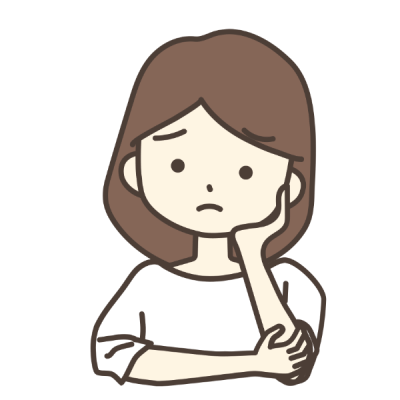
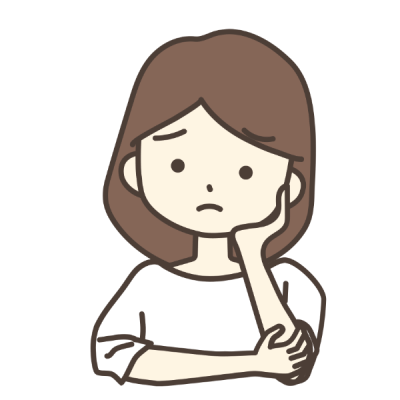
かといって差別化を意識するあまり視聴者のニーズから離れてしまうとダメですよね…
伸びる人は、伸びている動画に関して「差別化しない方が良い部分」と「差別化しても良い部分」をしっかりと見極めています。
分析において、伸びている動画に共通する核となるところは変化させず、伸びている動画でバリエーションがあるところ、すなわちオリジナリティを加えて差別化して良いところを理解するのが大切です。



同じジャンルの人気チャンネルを研究し、「競合が提供していない価値は何か」「視聴者が満たされていないニーズは何か」を見つけ出す癖をつけましょう!
さて、ここまでは特にYouTube運用のテクニカルな部分に関して、伸びる人と伸びない人の違いを整理してきました。
それでは、続いては伸びる人と伸びない人のYoTube運用に対する姿勢・精神面での違いに関しても見ていきましょう。
YouTubeで伸びる人と伸びない人の3つの違い(マインド面)
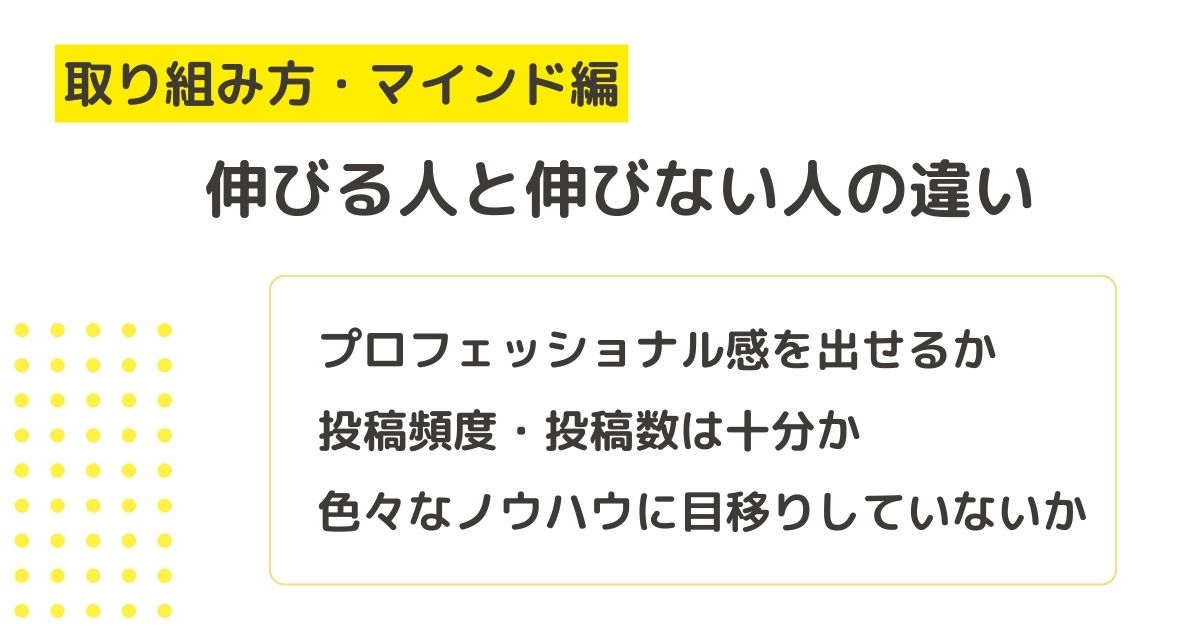
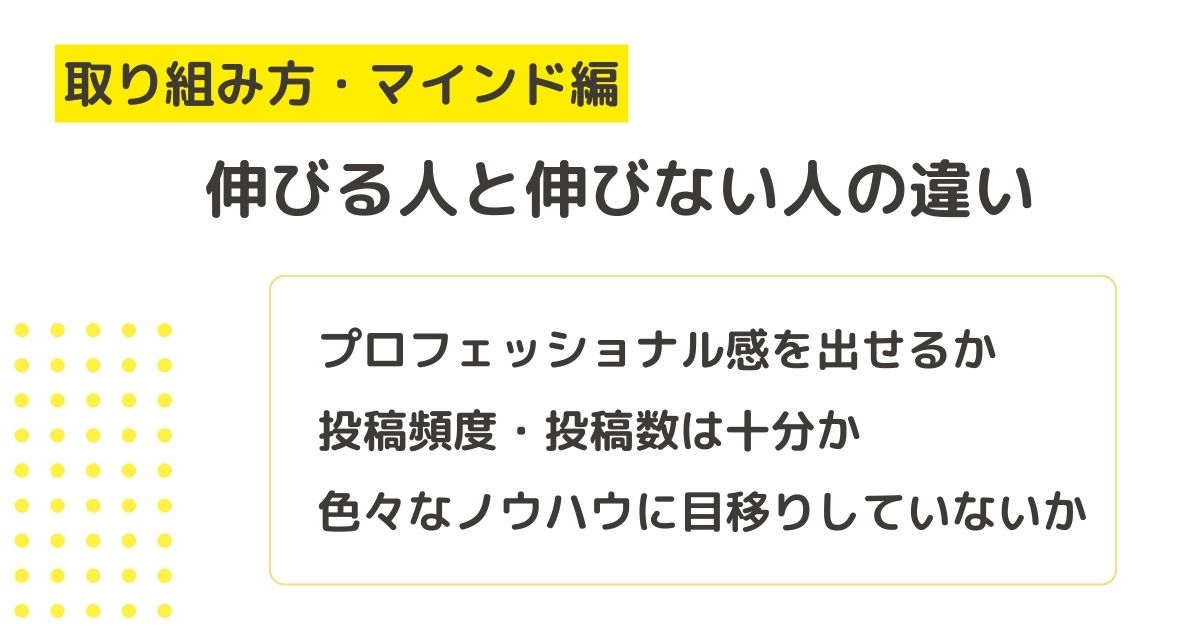
YouTubeに取り組む姿勢は時としてテクニカルな施策より重要な意味を持ちます。
ここではYouTube運用のマインドに関わる次の3つのポイントについて解説。
- プロ感を出せるか
- 投稿頻度・投稿数は十分か
- 色々なノウハウに目移りしていないか
YouTubeが伸び悩んでいて、マインドが下がり気味という方もしっかりと確認して今後のYouTube運用に活かしていってください。
プロ感を出せるか
YouTubeでは、視聴者に「プロフェッショナル」な印象を与えられるかどうかが重要な成功要因になります。
ここでいう「プロ感」とは単に高価な機材やツールを使うことではなく、コンテンツ全体の質や信頼性などの印象を指します。
- 映像・音声の品質
- サムネイル
- 効果的な編集う
- 構成力
- ブランディング
- リサーチ・分析
上記のようなYouTube制作の過程一つ一つにプロフェッショナルであるかどうかが現れます。
YouTubeをやるとなれば長年運用歴のあるプロも副業で始める初心者も関係なく競合になるため、いかにYouTubeに対してプロ意識を持って取り組むかが大きな差となって現れるでしょう。
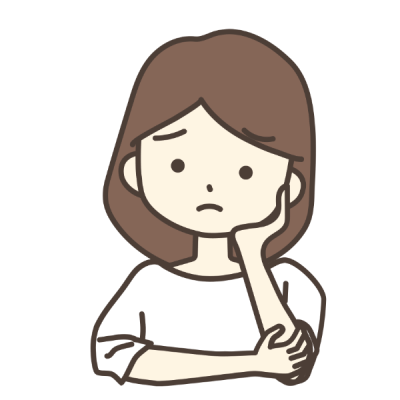
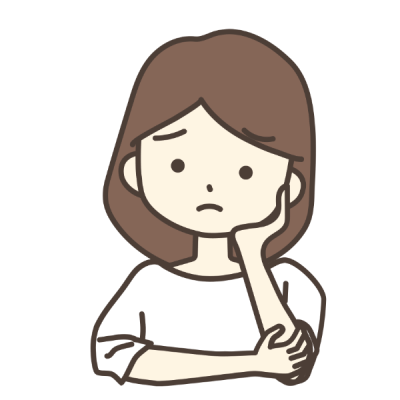
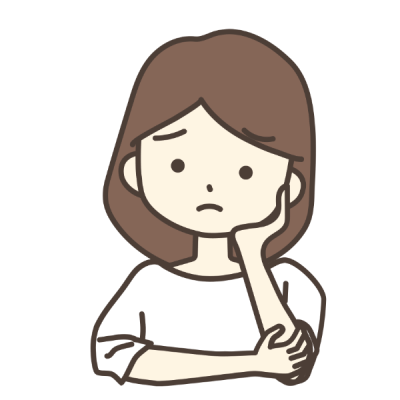
でもいきなりプロのような動画を作ることはできません。



最初のうちは多少クオリティが劣るのは仕方ないかもしれませんが、自分ができないことは外注化する方法がおすすめです。
動画編集の技術などをゼロから身につけようとすると大変ですが、クラウドソーシングを利用すれば比較的安い料金で作業の依頼が可能。
編集作業に費やす時間も減るため、分析や戦略の立案などより重要な作業に力を注ぐこともでき、全体的なクオリティはさらに向上します。
少しのプロ意識でコンテンツの質に差が現れるので、YouTube運用のプロとしての自覚を持ちましょう。



一つ一つの作業に関しては初心者でも適切に外注化ができれば、全体としてプロっぽいコンテンツが作れますね!
投稿頻度・投稿数は十分か
YouTube運用に限らず、ビジネスにおいてはスピードや量が大切です。
いかに早くたくさん行動をするかによって、得られる成果も変わりますし、フィードバックの精度にも関係するでしょう。
また、YouTubeのアルゴリズムと視聴者との関係性構築においても投稿頻度は重要な要素です。



どれだけYouTubeに取り組めるか、成功には十分な作業量が不可欠です。
客観的な数字として投稿頻度や投稿数を把握して、適切な量をこなせているかを確認しましょう。
投稿に関してはベンチマークとなるチャンネルを上回るようにします。
ベンチマークチャンネルとは、チャンネル開設日が3ヶ月以内(最近であればあるほど良い)、自分の少し先を行っている”同じジャンル”のチャンネルのこと。
ベンチマークチャンネルが週3本の頻度で投稿しているのであれば、自分はそれ以上の頻度で出す必要があります。
もちろん、投稿頻度や投稿数だけでなく、コンテンツの質もベンチマークを超えるようにしましょう。



質も量もベンチマークを超えることを意識するんですね!
伸びる人は投稿数を維持し、クオリティも高まっていきますが、逆に伸びない人は本人は頑張っているつもりでも問題を抱えている場合が多いです。
- 不規則な投稿頻度
- 長期間の休止期間
- 量を優先した質の低下
- モチベーション依存の運用体制
特に初心者の方に見られやすいので注意しましょう。
視聴者は定期的にコンテンツを楽しみにするようになるため、説明欄で投稿スケジュールを明示して視聴者の期待を管理することも効果的です。
質と量のどちらを大切にするかという問題は取り上げられることが多いですが、十分な投稿数・データがなければ改善のためのデータも不十分になってしまいます。



YouTubeで稼ぐのを目指したものの燃え尽き症候群にならないように、初心を思い出してたくさんコンテンツを出していきます!
色々なノウハウに目移りしていないか
投稿頻度・投稿数に加えてYouTubeで成功するためには、一貫性と忍耐も必要となります。
多くのクリエイターが陥る罠の一つが、様々な戦略や手法に振り回されること。逆に、YouTubeで伸びる人には次の特徴がよく見られます。
- 長期的な視点
- 軸となる戦略への集中
- 成功事例の本質的な理解
一方で、伸びない人は少し試してうまくいかなければすぐに別の方法に目移りしてしまいます。
流行りの手法だからといって自分のコンテンツに合うかどうかの検討なしに取り入れることもしばしば。
ノウハウは一貫性があってこそ効果を発揮する面があるので、初心者のうちは、複数のノウハウの良いとこ取りをしようと勝手にカスタマイズするのも実は危険な行為です。



XやYouTubeなどで様々なノウハウが紹介されますが、何でも鵜呑みにせずに軸となる戦略を大切にするようにしたいです。
以上が主にメンタルやYouTubeに対する姿勢に関連する伸びる人と伸びない人の違いでした。
いずれも重要な心構えなので、長期的に意識が途切れないようにしましょう。
【5つのポイント】YouTubeで伸びる人になるために伸びない人がすべきこと
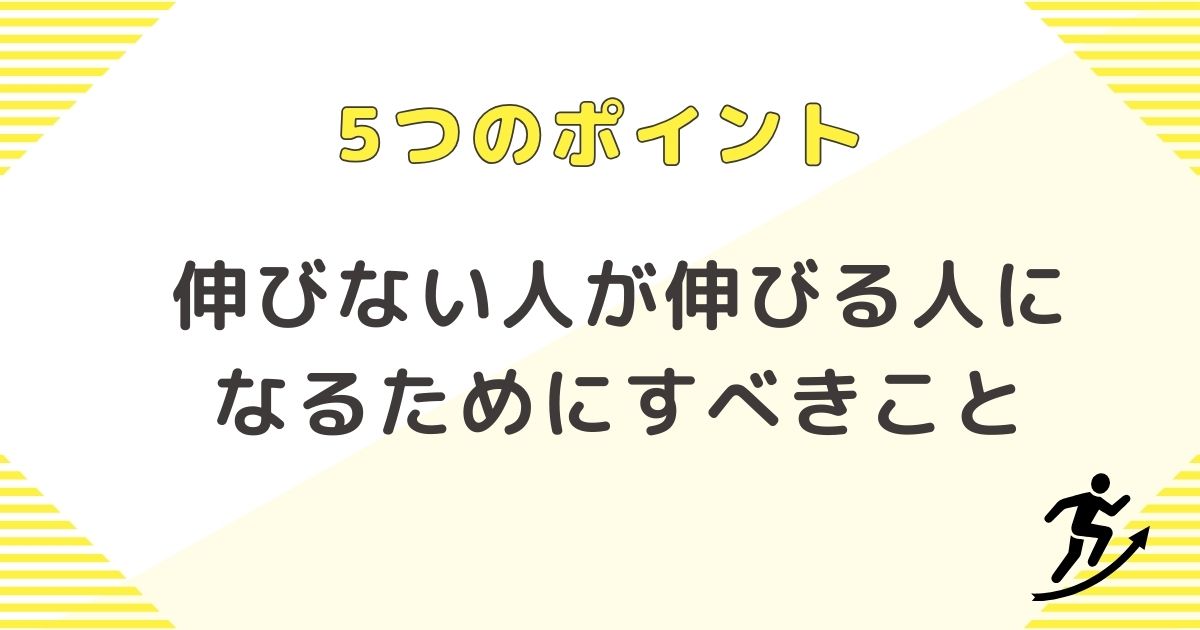
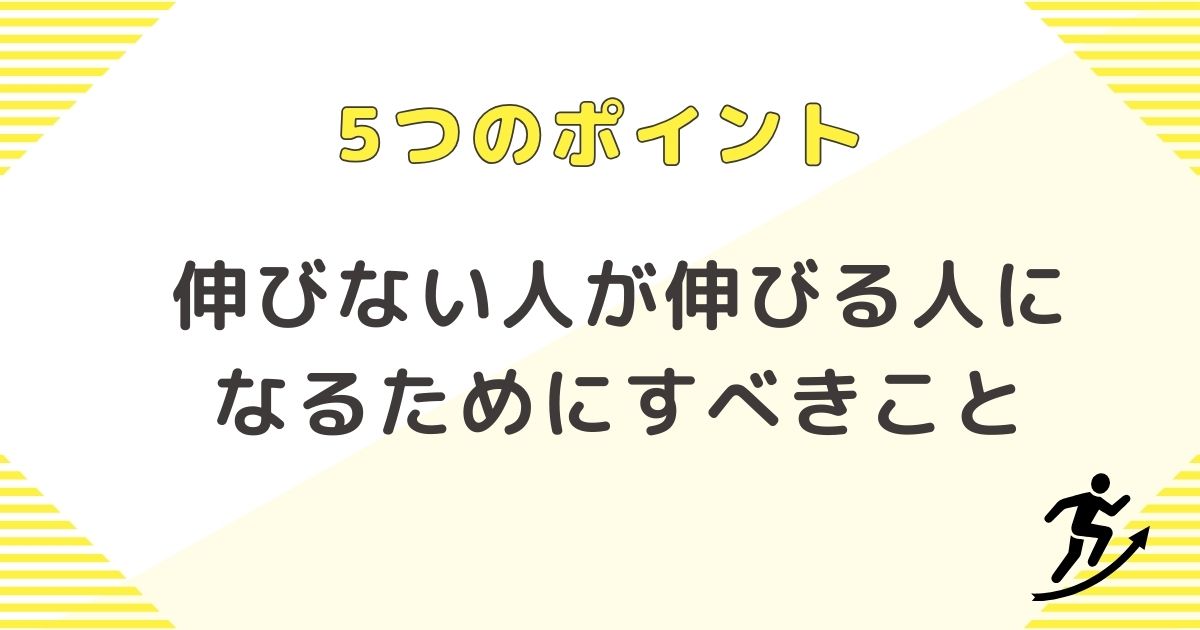
続いては、今YouTubeで伸びていない人が今後伸びる人になるためにすべきことをご紹介していきます。
必ずしも伸びている人と伸びていない人に才能の差があるわけではなく、ほんの少しの変化を加えるだけで、劇的に伸びるようになるというケースも。
YouTubeで伸びる人になりたいという人は、次の5つの項目を意識しましょう。
- 目的意識を明確に持つ
- 精度の高い分析を行う
- 伸びない原因を徹底的に特定する
- 自分に合った運用方法を見つける
- 経験者にアドバイスをもらう
多くのYouTube運用者を見てきて分かった伸びない人が伸びる人になるポイントを見ていきます。
目的意識を明確に持つ
まず最初の伸びる人になるためのポイントは「目的意識」に関してです。
ここでいう目的意識は、YouTube運用を行う上でのそもそもの大きな目的と運用の中で生じてくる一つ一つの作業に関する目的という2つの観点があります。
- 大きな目的:なぜYouTube運用をするのか
- 小さな目的:その作業をなぜ行うのか
大きな目的としては、例えば「子どもとの時間も大切にできる融通の利く仕事で子どもの養育費を十分に安定的に稼げるようになる」などが当てはまります。
大きな目的を明確にすることはモチベーションの維持に加えて、YouTube運用の大きな戦略を考えていく上で非常に重要です。
単なる精神論ではなく、チャンネル成長のための具体的な戦略の基盤となります。



日々のモチベーションやつらい時期を乗り越える力として大きな役割を果たしてくれますよね。



達成したい目標と共に、紙に書いてよく見える場所に貼っておくのがおすすめです!
小さな目的の意識は、作業の効率や効果を最大限に高めます。
何の目的も持たずにただ何となく作業を行っていても結果にはつながりません。
- なぜこの作業を行うのか
- 最終的にどうなれば良いのか
- 目的を達成するのにもっと良い方法はないか
これらを日々の作業で意識するようにすれば、現時点で伸びていなかったとしても将来的に大きく伸びるようになります。
精度の高い分析を行う
YouTubeで伸びていない原因を突き止め、効果的な改善策を見つけるためには、データに基づいた精度の高い分析が不可欠です。
感覚や印象だけでなく、客観的な数字を見ることで、具体的な問題点と改善の方向性が見えてきます。
- 視聴維持率
- クリック率
- 視聴者層データ
- エンゲージメント率
- 流入経路
上記の他にも様々なデータがあるので、状況に応じて使い分けるようにしましょう。
特に、伸びていない人は分析しているつもりでも分析が甘い場合が多いです。
自分が運用しているチャンネルと競合のチャンネルについて十分な量のデータを集める必要があります。



分析の際には分析ツールも効果的に使えると良いでしょう。
次のツールはYouTube運用全体において使用頻度が高いツールです。
参考としてまとめておきますので、最低限の機能は使いこなして、より精度の高い効率的な分析を行いましょう。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| YouTubeアナリティクス | 自分のチャンネルの基本的な情報を無料で確認できる |
| vidIQ | 競合の調査やSEOの最適化を支援するツール |
| キーワードプランナー | キーワードや需要に関して無料でデータを得られる |
| ahrefs | キーワードや需要に関して詳細なデータを得られる |
| NoxInfluencer | 競合のインフルエンサーの分析を行える |
| kamuitracker | 競合のチャンネルやトレンドの分析ができる |
精度の高い分析を継続的に行うことで、自分の曖昧な感覚に頼るのではなく、データに基づいた意思決定につながります。
これにより、限られたリソースを最も効果的な改善点に集中投下することが可能になり、チャンネルの成長速度を加速させることができるでしょう。



分析だけで終わるのではなく、仮説の設定、実行・検証もセットにして改善のサイクルを確立してください!
伸びない原因を徹底的に特定する
YouTubeチャンネルが伸び悩んでいる場合、その原因を正確に特定することが改善の第一歩です。
問題と解決策が一致していなければ、どれだけ努力をしても十分な結果が得られません。逆に、原因の特定とアプローチがうまくいけば、今まで伸びていなかった人でもどんどん伸びていきます。
多くのクリエイターは問題の表面だけを見た対症療法的な改善を試みますが、根本的な原因を特定し解決することが長期的な成長につながります。
| 分類 | 具体的な原因の例 |
|---|---|
| コンテンツ関連 | 価値提供の不足 |
| エンターテイメントの不足 | |
| 新規性の欠如 | |
| 戦略・方向性 | 需要との不一致 |
| ターゲットとのミスマッチ | |
| ブランディングの失敗 | |
| プロモーション不足 | |
| 技術・品質 | 低品質な素材 |
| 編集技術に乏しい | |
| サムネイル・タイトルが不適切 |
例えば一般的な原因を挙げるだけでも、上記のように様々なものが考えられます。
当然、これら一つ一つにアプローチする解決策も異なります。



これらの原因を特定するためにも先ほどの分析が大切なんですね。
病気になって病院に行った場合に、的確な診断なしには効果的な治療がなされないことは容易に想像がつくでしょう。伸びない状態にあるYouTubeに関してもこれと同じです。
原因を徹底的に特定することは時間と労力がかかりますが、原因が絞り込めると施策を打つ際の優先順位付けや見通しがわかりやすくなります。



伸びない理由が分からないという方に向けて無料相談も行っていますので、ご希望の方は公式LINEからご相談ください。
>>YouTube運用のプロに相談をする
自分に合った運用方法を見つける
YouTubeで成功するためには、一般的なベストプラクティスを盲目的に追従するのではなく、自分の強み、制約条件、目標に合った独自の運用方法を確立するのも大切。
ここでは持続可能で効果的なYouTube運用法を見つけるためのステップを解説します。



実際に自分の状況と照らし合わせて考えてみましょう!
まずは準備段階からです!
自分に適したYouTube運用方法を見つけるために、次の手順に従って自己分析や制約条件を明確化しておきましょう。
YouTubeの運用は短期間で完結する訳ではありません。
特に初めのうちは一定の作業量が必要になるため、あらかじめ時間的な制約を把握しておくことは非常に重要です。
1日あるいは週にどれくらいの時間YouTubeに割けるか、まとまった時間を取ることが可能かどうか確認しておきましょう。



会社員の方は本業との兼ね合い、ご家族がいらっしゃる方は家族の時間との調整などを考えなければなりません。



YouTube運用を進めるにあたって家族と相談しておくのも良いかもしれませんね。
続いて、YouTubeにおける自分の強みを知る作業です。
次の項目について、得意とするものや自分を特徴づけるものがあるかチェックしてみてください。
- データ分析や戦略立案
- 話術・プレゼンテーション能力
- 編集技術
- デザイン
- 人柄・キャラクター
- 容姿や声
これらに加えて、専門的な領域に関して知識や技術を持ってい場合は、それも大きな武器となります。



ユーモアのセンスがある→エンタメ要素強め
分析・リサーチが好き→解説系
など気軽に捉えて良いでしょう。
自分にはこれといったものがないという方も安心してください。
自分の容姿や人柄といった固有の要素にとらわれない非属人のYouTube運用でも、安定的に成果を上げることは可能です。
詳しくは、非属人とは?YouTube非属人チャンネルの作り方と運用方法を徹底解説 の記事をご覧ください。
準備の最後として、自分が使えるリソースも把握しておきましょう。
実際にはYouTube運用は生活の中で継続的に行っていくため、リソースに関する情報はいろいろな戦略の中から最適なものを選ぶのに役立ちます。
- 機材:利用可能な撮影・録音機材
- 予算:チャンネル運営に投資できる金額
- 場所:撮影や編集が可能な環境
- サポート:協力者や外注できる人材
例えば、撮影・録音機材、YouTubeの撮影が可能な環境がないのであれば、外注や編集で動画制作が完結するようなチャネル運営方法を選択するのが良いでしょう。



実際に自分で書き出してみると頭の中が整理されて分かりやすいですね!
上記の準備を行った上で実際に運用を行って調整を加えていきます。
進めていく中で比較的初期段階で目安がつくのが投稿頻度や投稿数といった動画投稿のパターンに関するものです。
作業に一度取り組んでみることで、コンテンツ制作の過程で何にどれくらい時間やリソースが取られるか掴むことができるでしょう。



一連の流れを掴めたら、効率化やクオリティの向上を目指していきましょう!
同種の作業をまとめて行い、同時並行でコンテンツ制作を進めたり、テンプレートを作成したりすれば、日々のYouTube運用のハードルは下がります。
特定の作業が滞る、負担になるなどボトルネックになるものがあればツールや外注化を導入して、自分に合ったやり方をカスタマイズしていくのをおすすめします。
また、コンテンツをまとめて作りストックしておき、定期的に休息を取ったり、一緒に頑張れる仲間を見つけるなどのモチベーションの管理も重要です。



フルタイム勤務のクリエイターと家事・育児で忙しい主婦の方だと適切な運用方法は変わりますよね!



自分に合ったやり方が見つかれば、伸びない人も伸びるようになります!
経験者にアドバイスをもらう
ここまで、伸びない人が自分でYouTubeを伸ばすための方法をお伝えしてきましたが、YouTubeで成功するための道のりは、すでにその道を歩んできた経験者からのアドバイスを得ることで大幅に短縮できます。
未経験者が自分一人で悩むより、経験者に一言アドバイスをもらう方が伸びるケースもあるでしょう。
経験者にアドバイスを得ることには、以下のような大きなメリットがあります。
- 遠回りの防止
- 学習曲線の短縮
- 盲点の発見
- 業界の内部情報
- ネットワーク拡大
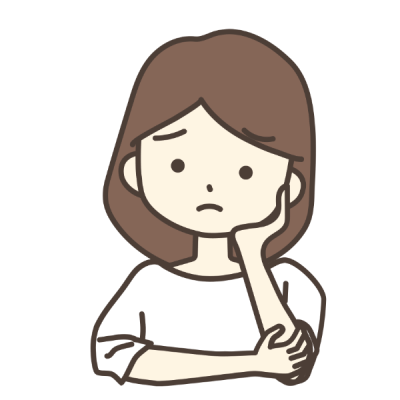
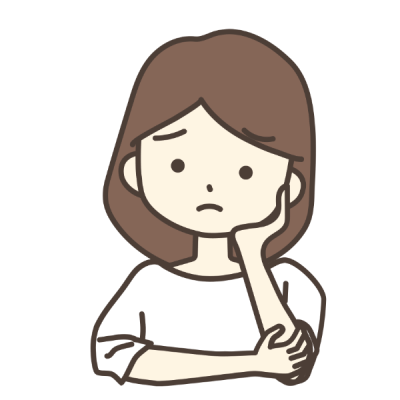
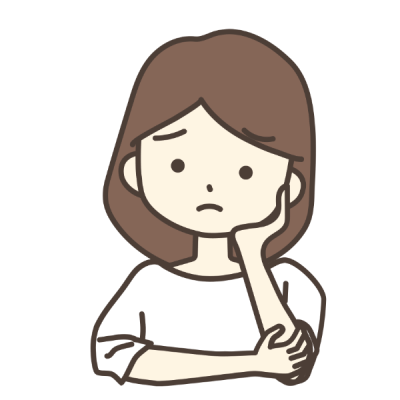
アドバイスは誰にもらうのが良いでしょうか。
経験者として簡単に思い浮かぶのは同じジャンルの先輩YouTuberだと思いますが、実は質の高い意見をもらうには不適切な場合があります。
一見、ジャンル特性を踏まえた有益なアドバイスをくれそうですが、ジャンルがかぶっていると競合になるため、有益な情報を得られない可能性も。
かといって、異なるジャンルのYouTuberにアドバイスを求めても、実情を把握していない可能性も。



おすすめは、経験豊富な実績のあるコンサルタントに問い合わせを行うことです。
多くの経験があるYouTubeコンサルタントの場合、日頃からYouTube運用における課題と向き合っているため、解像度の高い意見が得られる場合が多いです。
コンサル選びのポイントについては、個人か会社どっち?YouTubeコンサルのおすすめや選び方のコツを解説 の記事で詳しく解説をしています。
無料でチャンネル診断や相談を設けている人も多いので、積極的な利用をおすすめします。



私も公式LINEで最新のノウハウの発信や相談の受付を行なっているので、ご活用ください!
>>公式LINEに登録する
まとめ
最後にこの記事の内容をまとめます。
- YouTubeで伸びない人は需要が捉えられていない
- 伸ばすためにはジャンル選びや競合分析も大切
- 技術面だけでなくマインド面も整えていくべき
YouTubeで伸びる人と伸びない人には様々な違いがありますが、視聴者の需要を捉えられていなかったり、適切なジャンル選定を行えていなかったりする場合が多いです。
また、技術面だけでなく、YouTube運用全体に対する取り組み方・姿勢も長期的に伸ばす上で大きな差を生み出します。
これからのYouTubeで伸ばしたいという人は特に朗読系ジャンルがおすすめです。



公式LINEではノースキルからYouTubeを伸ばすためのノウハウを紹介しています。ぜひご活用ください。
>>公式LINEを登録する